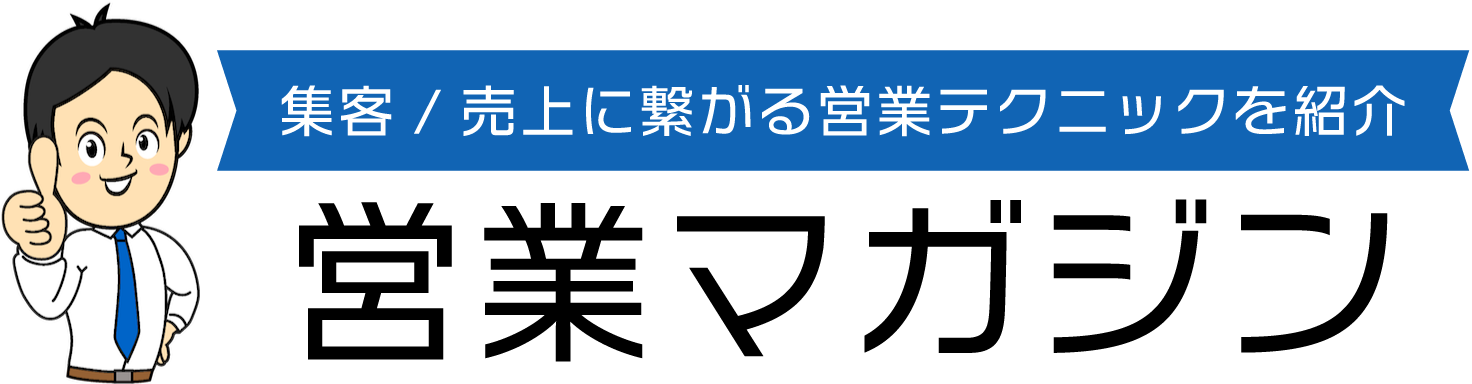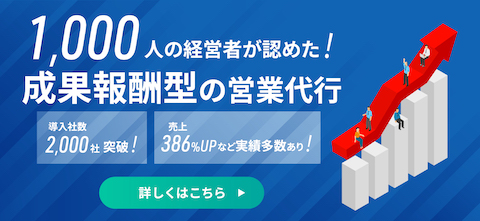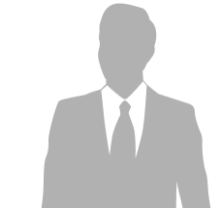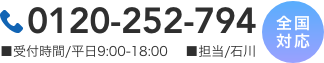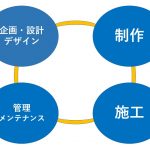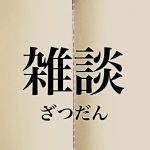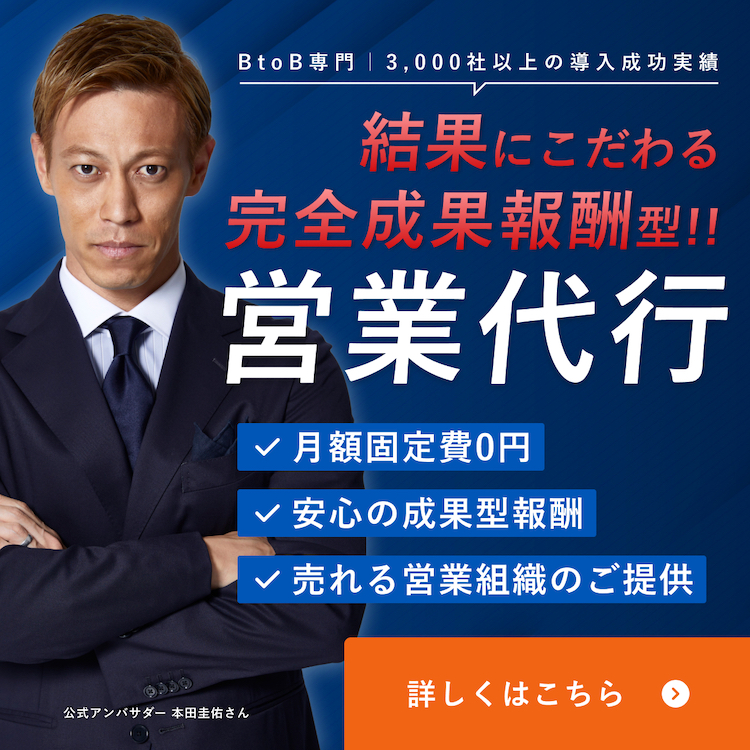中小企業の新規開拓の中で、なおざりにされていることが多い広報活動。その理由は「やる理由が分からない」「やりたくてもやり方が分からない」。しかし新規開拓において、とても重要です。前回は「中小企業の広報目標」について解説しました。目標が定まったら、次は具体的な行動です。中小企業の広報は大企業の広報と同じことをやってもうまくいきません。本記事では、中小企業がどのようにメディアリレーションをしたらよいか具体的に記述していきます。

もっと高収入で安定した会社に転職したいなら
若手ハイクラスに特化した転職サイト
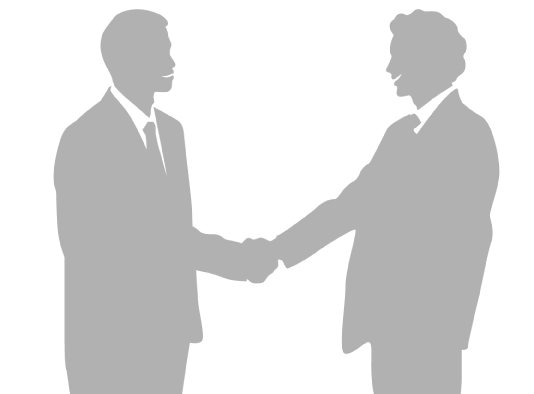
- 例1今の営業職は好きだけど給料や待遇に満足いかない
- 例2もう営業職は辞めたいけど他の職種に転職できるか不安
- 例3自分の将来、今の仕事のままでいいのかな?
- 例4貴重な時間や可能性を無駄にしているかも
- 例5私を欲しがっている企業がいるなら転職したい
支援品質満足度No.1
若手ハイクラス向け転職サイト「VIEW」に今すぐ登録
若手のキャリアアップを目指す案件が充実!
転職支援に留まらず、キャリア形成をサポートするエージェントからスカウトが届く!
大企業と中小企業の広報活動は全く別物
では早速質問です。社外に向けた広報活動はどういったことを想像されますか?
一般的に知られている広報の方法、例えば「プレスリリースを一斉配信する」「記者クラブにプレスリリースを持ち込む」等は、実は大企業の広報活動の方法で、中小企業には不向きです。中小企業が行うと効果がないばかりか、マイナスになってしまうこともあります。大企業はそもそも知名度があるので、社名だけでマスコミは興味を持ってもらえますが、中小企業は知名度がないので興味すら持ってもらえません。ネタを何度もむやみに一斉配信するのは、マスコミからしたら「またあの会社から来たけど、どうせ興味ないネタだろ」ということで、ネタ自体見られず、さらにうっとおしがられるという悪循環になってしまいます。つまり、大企業と中小企業の広報活動は全く別物なのです。
だからといって、中小企業は広報活動をやらないわけにはいきません。シリーズでも記述しているとおり、広報活動は中小企業には非常に重要です。中小企業が広報活動を行うにあたって重要なのは、自社のネタに興味のあるマスコミに対し、ピンポイントでマスコミが興味ある形でネタ提供をすることです。つまり、大企業よりも密なメディアリレーションが必要なのです。
そもそもメディアリレーションとは?
メディアリレーションとは、メディアとの関係構築をすることで、発信者側(広報担当)とメディアがお互い信頼しあった上で、コミュニケーションを継続的にとっていくことです。この関係が本当に構築できていれば、メディアの担当者が替わったとしても後任を紹介してくれ、その媒体と継続的な関係は築けます。記者側からも後任者を紹介したいと言ってくれますし、引継ぎもしてくれるはずです。
前述したように大企業はすでに知名度があり、上場企業なら担当記者がいて、関係性もできやすい環境がすでにあります。しかし、中小企業はこの関係がゼロからのスタートなので、大企業に比べると大変なのです。逆に言えば、この関係構築の入り口の部分を攻略してしまえば、大企業と変わらないメディアとの関係構築ができます。むしろ小回りが利いて、メディアからの要望にも素早く対応できる中小企業の広報担当者のほうが、大企業よりも深い関係を構築しやすいのです。
中小企業の広報担当者はどのようにメディアリレーションをしたらよいのか?
では中小企業の広報担当者はどのようにメディアリレーションをしたらよいのでしょうか?新聞社へのメディアリレーションを例にして、下記5ステップを解説していきます。
- 自社分析
- ターゲット媒体の選定(担当記者・編集者の選定)
- プレスリリース・企画書の作成
- プレゼンテーション・取材
- メディア露出の御礼、担当者の興味・関心の深堀り
自社分析
まず自社のサービス・商材が誰に対するサービスを提供しているかを考えてみてください。「BtoB」なのか「BtoC」なのか、もしくは業界や会社の規模感、地域密着なのかグローバル展開しているのか、最先端の仕事をしているのか、古くからの伝統を守っている企業なのか、誰にどんな影響を与えている会社なのか・・・etc。
メディアはあくまで社会的影響のあるものに興味を持ち、取材・記事にします。つまり「自社が社会に与える影響が何なのか」を整理することで、自社に対してメディアが興味を持つ軸を決めます。
ターゲット媒体の選定(担当記者・編集者の選定)
自社分析ができれば、次はアプローチする媒体選定をしていきます。新聞社もいろいろな新聞社がありますね。「読売新聞」「朝日新聞」「毎日新聞」「産経新聞」のような全国紙もあれば、「日本経済新聞」「日経産業新聞」「日経MJ」のような経済紙、業界紙や専門紙など様々なタイプの新聞があります。また地方紙でも、特定地域の配布数が全国紙よりも多い新聞もあったりします。その中で、各紙の特性と自社の相性の良い(記事にしてくれる可能性の高い)新聞社をピックアップします。
さらに過去、自社の商材・サービスに近い記事を取り上げている紙面やコーナー、記事を書いている記者を特定します。この特定作業、とても大変だと思いますよね。図書館に行って、過去の記事を全てチェックするのかと思うと途方に暮れてしまいますが、そんな方のために良いサービスがあります。「日経テレコン」です。
日経テレコンは広報担当の必須ツール
日経テレコンとは、過去30年分の新聞・雑誌記事を中心に、国内外の企業データベース、人物プロフィルなど、幅広いビジネス情報を収録。戦略立案、業界分析、M&A、競合比較、リスク管理、海外進出。情報を必要とするすべての人々にとって欠かせないビジネスツール。
つまり日経テレコンは過去30年分のメディア記事を調べることができます。こちらをうまく使って、過去に自社サービスに近い商材・サービスの記事を検索して、どのコーナーで取り上げられたか、どの記者が記事を書いていたかを一瞬にして特定することができます。日経テレコンは広報担当の作業時間を大幅に削減してくれる必須ツールなのです。そして自社に興味を持つ可能性のある記者が特定さえできれば、取材・記事化へはかなり近づきます。
プレスリリース・企画書の作成
アプローチする記者が決まったら、次はその記者が興味を持つプレスリリースの作成です。プレスリリースの書き方はノウハウ本などでもよく紹介されているので、そちらを参考にしてもらえればOKですが、ポイントは「記者が興味を持っているネタを、時事に絡めて端的に表現できるか」です。また、記者はあいまいな表現を嫌います。新聞を見てみてください。「かなり」「とても」というあいまいな表記よりも「売上○○円見込み」や「○月○日サービス開始」など具体的な数値で、表現している記事が多いです。つまり記者がプレスリリースを読んで、そのまま記事にできるくらいのプレスリリースなら、記者は「この広報担当者、わかっているな」となり、評価が高まります。
プレゼンテーション・取材
プレスリリースに興味を持ってもらったら、次は取材につなげるプレゼンテーションです。こちらもノウハウ本などでよく紹介されているので、私がお伝えするポイントは1つです。プレゼンテーションをする前に、「日経テレコン」で調べた、その記者の過去記事に絡めた話題をして、「あなたの記事をいつも楽しく読ませてもらっている」という印象を記者に与えることです。記者からすれば、自分の記事を読んでくれている人に対して悪くは思わないので、好意的に接してくれ、プレゼンテーションも非常にやりやすくなります。あとはノウハウ本のやり方でプレゼンテーションを行えば、かなりの確率で取材につながります。
メディア露出の御礼、担当者の興味・関心の深堀り
無事、取材されたネタが記事化されたら、次のアクションは御礼の連絡です。ここで、できる広報担当とできない広報担当の差が生まれます。できる広報担当者は、次のアクションに向け、記者と会食を行います。会食の目的は、記者が「なぜ記者になったか」のルーツや興味関心ネタが何なのかを確認し、次のネタを仕込むための情報を集めることです。記者もやはり人間なので、お酒が入ると、より素に近い状態で接してくれます。ここで仲良くなり、しっかりとその記者の興味関心情報が得れると、次回提供するネタのイメージが湧くはずです。
ここまで仲良くなってしまえば、あとは興味に沿ったネタを時事に合わせて提供するだけなので、そこまで難しくありません。また記者の担当が替わったとしても、ほしい情報を的確にくれる広報担当者という認識のもと、後任も紹介してくれるはずです。
記事のまとめ
この記事では中小企業がどのようにメディアリレーションをしたらよいか具体的に記述してきました。
中小企業のメディアリレーションは、関係構築の入り口の部分を攻略してしまえば、大企業と変わらないメディアとの関係構築ができます。むしろ中小企業の広報担当者のほうが、大企業よりも深い関係を構築しやすいのです。またマスコミもあくまで人間です。相手の興味関心を的確につかんで、そのネタを最適なタイミングで提供していくことで、より良い関係構築をすることができるでしょう。